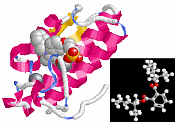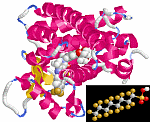環境ホルモン問題は終わっていない
水俣病が終わっていないように,微量の合成化学物質の生態系への影響を考えるきっかけとなるべきだった環境ホルモン問題も終わっていないことを,
が定期的に教えてくれる。この問題に脚光が当たったのは,次々と登場する新規合成化学物質の生産量の多さと環境中への排出,分析化学の発達により微量物質の検出が可能になったこと,生体分子の複雑な働きが少しずつわかってきたこと,が大きな要因になっていると考えている。当初は社会的に過剰な反応があったし,研究予算の過分なあるいは偏った配分があったのは事実だが,合成化学物質と生物との相互作用やあるべき関係を真摯に考え続けなければならないのは間違いのない事実である。
いろいろあってチェックが遅れていた同レター最新号(2007/03)を数日前に見て,上記要因を踏まえた研究が着実に進んでいることに安堵すると同時に,その研究成果の意味することの重さに暗澹たる気持ちになる。
- 環境ホルモン学会ニュースレター,Vol.9 No.4(2007/03)の解説より抜粋
- 工藤一郎,『精子におけるホスホリパーゼA2の発現と機能』
- 藤田正一,『化学物質の感受性を決定するP450及び第II相系抱合酵素の動物種差・系統差』 ※参考:P450データ集
- 小泉昭夫,『脳の情動における毒性学―Anorexigensの毒科学』 ※PFOS,PFOAについてははっ水剤・難燃剤の生物体内蓄積性参照